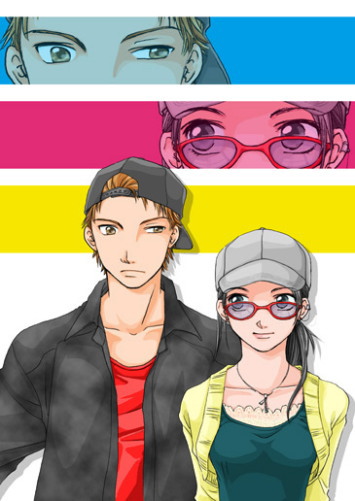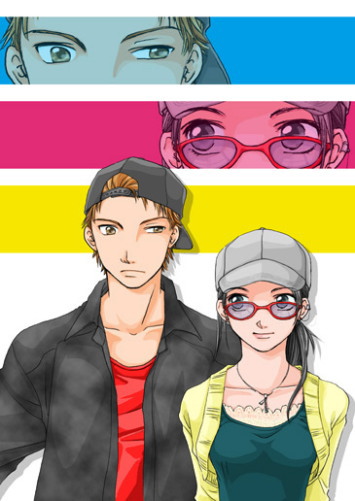遊び仲間。ケンカ友達。腐れ縁。
よく言われる二人の関係はこんな感じ。
どれも正しくて、だけどどれも微妙に違う。
人によっては友達以上恋人未満なんて複雑怪奇なお言葉をくれたりもするけど、以上とか未満とか数学の方程式じゃないんだからさ。
うん、まぁ半分位はお互いに「そう」なんだろうなってのはあるんだけど、とりあえずは、なし崩しにオツキアイになだれ込む一歩手前。
一応さ、オンナノコとしてはやっぱり言われてみたいな、とか思ったりもするわけで。
っていうか、何か私から言うのって負けって感じして悔しいじゃん?
+++ 関係。+++
最初は『今日って天気いいよな?』の台詞を聞き間違えたのかと思った。
それくらい普通に、いつもの無表情のままで聞いてきたから。
だけど聞き返した私に、彼はやっぱり表情を変えずに同じ質問を繰り返す。
「俺たちの関係って何なんだ?」
爽やかに晴れた日曜日の午後、映画と買物を楽しんだ後に立ち寄ったカフェ。
目の前には春の新作・トリプルベリーパフェが紅茶と共に鎮座し、私に食べて貰えるのを今か今かと待っているのに、同席した人間はそれに気づく様子もない。
確かにいつもなら相手の事なんてお構いなしに食べる私だから、それも無理はないかもしれないけど。
けど、だからって『二人の関係』なんていう重大な問題を、お茶のついでに持ち出したこの男に罪はないなんて絶対認めない。
こっちはそれ聞いた途端、心臓があり得ないくらいの速さで活動しだしたっていうのに、何ゆったりコーヒーなんか飲んでんのよ!
「何なの、急に?」
精一杯平静を装って言ったのだけれど、声が微かに震えてしまった自分が悔しい。
それをごまかすようにスプーンを取り上げてパフェを食べ始めた私に、彼はわずかに眉を顰める。
「質問を質問で返すなよ」
「いきなり変なこと聞くからでしょ、何か言われた?」
重ねて尋ねると、ほぼ肯定に近い沈黙が返ってきて私は首を傾げた。
だってそんな事『何を今さら』ってぐらい、さんざん訊かれてる。
「いいだろ、別に。 だいたい俺のが先に聞いたんだけど」
「答える義務ないし?」
「じゃあ俺も答える必要ないよな」
「はいはい。 じゃ、この話は終わりってコトで」
そう締めくくると、彼は苦虫を噛み潰したような顔をした。
どうしてこう不機嫌そうな表情だけ表に出やすいんだろう、この男は。
そのまま少し荒っぽい仕草でコーヒーをかき回していた彼は、やがてそれを止めると再び私に視線を戻した。
「で、結局どうなんだ?」
「もー、しつっこいなぁ。 そんなの遊ぶのに支障ないじゃん」
私たちの関係?そんなことこっちが聞きたいっての。
「あ、まさか可愛い後輩にでも告られたとか。 先輩、お二人の関係って何なんですかぁ?」
舌足らずな甘い声を真似てみせながら、頭の中で候補者を探す。
っとに、一人じゃないってのが質悪いよね。 みんな趣味悪いっていうか。
自分の事は棚に上げ、私は紅茶に口をつけた。
そっとカップ越しに彼を見ると、相変わらず読めない無表情で窓の外を眺めている。
まさか、だよね?
「かもな」
「……っ!?」
ぼそりと呟かれた台詞に、思わず吹き出しそうになって慌てて堪える。
「かもなって………誰? 私の知ってる子?」
「答える義務、ないだろ」
さっきの私の台詞を逆手にとって、彼は素っ気なく言った。
暗に私には関係ないと言われた気がして、一瞬息が止まる。
「そ、れは…けど、教えてくれたっていいじゃない、私とアンタの仲でしょ」
「その『仲』について聞いた俺の質問無視したの、誰だっけ?」
しれっと言い放ちコーヒーのお代わりを頼む彼を睨みつけるが、威力の程は分からない。
ああもう、だからなんでそんな無表情なのよ!
いらいらしながらパフェをザクザクとつつき回すと、綺麗に飾られていたラズベリーがクリームに沈んだ。
「だいたいね、一人一人違う人間同士の関係を一言でくくろうってのが無理なのよ」
言いながら、私はスプーンを相手に突きつけた。
尊大に胸を張って…って我ながらなんて可愛くない仕草。
誰かさんみたいに小首を傾げて上目遣い、なんてのはさすがに柄じゃないけれど、でももう少し何か。
とりあえずスプーンは下げて、紅茶を一口。
「恋人の定義だって人それぞれなんだからさ」
まぁな、と彼が呟いたので、納得したのかと思ったのもつかの間
「確かにそれも一理あるとは思うが、世間ではそういうのも全部ひっくるめて一言でくくるよな」
悔しいくらいに正論を返され、私はまたもや言葉に詰まる。
そこでふと思い出したかのように、彼が目を上げた。
「ちなみに、ジブンの恋人の定義ってのは?」
「へ? え、あー、やっぱ両思い基本? 告られたからとりあえず、ってのはちょっとねー」
突然の事に面喰らった私が素でそう答えると、彼はちょっとだけ目を見開いて、へぇ、と呟いた。
何よ、どうせ意外に乙女趣味だとか思って──
「俺も」
「…………」
あのさ、普段無愛想な人間が笑うのって、反則技だと思うんだけど。
以前、際どいところを歩いていた私の心は、この笑顔に後押し、もとい突き飛ばされるように、恋に転がり落ちたのだ。
それからというもの、結構居心地いいんだよね、なんて思う反面、どっかの誰かにかっ攫われるんじゃないかって不安は日増しに強くなってく。
今の所はまだ、ふとした拍子に溢れそうになる感情をなんとか抑え込んで、この関係をキープしているけれど。
自分のモノなのに、全く思い通りにならない心臓をもてあましながら、私はパフェを口に入れた。
もちろん、味なんてもう分からなくて、見た目だって頭の中と同じようにぐちゃぐちゃで。
悔しいったらない。
「さっきの、そんなにくくりたいならアンタが決めればいいんじゃないの?」
苦し紛れに出した提案に、彼は露骨に顔をしかめるけれど、そんな顔したって知らない。
だって、私の望む選択肢は一つしかないのに。
それを告げた途端、ちょっとでもアンタの表情が曇ったら、私はどうすればいいの?
「俺が恋人だって決めれば、そうなんの? 矛盾してないか、それ」
してない。
そう答える代わりに、私は相手をまっすぐ見返した。
「じゃあアンタはどうなのよ。 私が言ってそれで決まり、それでいいの?」
……………………………………ねえ。
爽やかな春の午後に、お気に入りのカフェで、好きな人と。
なんで睨み合わなきゃなんないわけ?
いや、そりゃ私の態度も問題だとは思うけどさ。
2人っきりよ、2人っきり。
ちょっとぐらいは甘い雰囲気になってもいいと思わない?
「……埒があかねぇっつーの」
しばらくしてそう呟いた彼は、再度お代わりを頼んでから口を開いた。
「あー、つまりな、昨日告白予約を聞いたんだ」
「ふうん………って予約?」
やっぱり、と落ち込みかけて、ふと思う。
本人に予約するのって告白とどう違うわけ?
そう私が首をかしげると、彼は元の──よりも少し不機嫌そうに見える無表情に戻って肩を竦めた。
「俺にじゃなくて、ジブンに告白する、だから予約だろ?」
「………は?」
へー、私って人気者。
じゃなくて。
「……………予約って、私に喋っちゃっていいの?」
いいだろ、名前言ってないし、とうそぶいて彼はコーヒーを飲んだ。
「告白するならさっさとすりゃいいのに、あのバカいちいち宣言なんかするから……」
ぼそぼそと独り言のように呟き、またコーヒーをあおる。
私はふて腐れたようにそっぽを向いている彼に気づかれないよう、そっと深呼吸した。
「宣言なんかするから、何?」
ごふ。
飲みかけたコーヒーにむせる彼。
激しく咳き込んでいるところへ、大丈夫?なんて優しくナプキンを差し出して。
にっこり微笑んでみせたら、目元を赤くしつつも睨み返された。
次いで、はぁーと思いきりため息をつく。
「あーもー、俺から言うのってどうも負けって気がしてやだったんだけどなぁ」
……………へ?
何の事か分からず、思わずまじまじと相手の顔を見つめると、居心地悪そうに視線を泳がせた彼が何度目かのお代わりを。
「ってゆーか、コーヒー飲み過ぎ」
「のど渇くんだから仕方ないだろ…って何、素で流してんだ、こら」
彼がジロリとこちらを睨んだが、あいにくと私の思考回路はまだ答えをはじき出してない。
首をかしげる私を見て、彼はもう一度大きなため息をついて髪をかき回す。
そうして、こちらを向いた顔に今度こそ心臓がおかしくなるかと思った。
照れたような柔らかい苦笑に、体が勝手に熱くなる。
うわ、ちょ、待っ…やばいってば。だって。でも。
もはやごまかしようもない位、赤くなっているはずの顔を隠そうと私は慌ててうつむく。
「も、いーや、負けで。 そんなんどうでもいい位、ベタ惚れだから」
直後、頭の上から降ってきたセリフに、頭をガンと殴られたようなショックを受けた。
いい、いま、今何て?
負けでいい、ってことは私の勝ち………って問題はそこじゃなく!
半ばパニックに陥った私に向かって、彼が畳み掛けるように続ける。
「という事で、さっきの質問。 俺たちの関係、何て説明すればいい?」
彼の声は、逃げる事を許さない真剣な響きを帯びていた。
「う、え、えーと。 じゃぁ、こ、恋人ってことで、いいんじゃない?」
「だよな」
至極あっさりとしたその声に慌てて顔を上げると、彼がにやりと口元を歪めた。
「そう思って、売約済っつっといた」
「んな…!?」
柔らかい、ではなくしてやったりって感じの満足げな笑顔に、私は足下がグラリと揺れたような感覚に陥る。
「ちょ、それ……っ」
「事後承諾ってやつ? とりあえずウソつきにはならずに済んだな」
「……っ! ば、売約済って、人を商品みたいに…っ! だいたい私が断ったらどうする気だったわけ!?」
今さら仮定の話をしても意味がないのだけれど、読まれてたと思うと悔しくて仕方がない。
さっきのセリフも笑顔も全部演技だったというのだろうか。
「ああ別に、断られても諦める気なかったし」
「〜〜〜〜〜っっ」
さらりととんでもない事を口にして、同じ事だろう?と笑う。
憎たらしいくらい余裕の、けれどめったに見られない満面の笑みが今日は大盤振る舞い。
その笑顔にいちいち跳ねる心臓が恨めしい。
悔しさとか嬉しさとか色々な感情が入り交じって、収拾がつかなくなった私は勢いよく立ち上がった。
「帰る」
「って、おい」
紅茶もパフェも半分近く残したまま、いつもなら払うお勘定もほったらかしにして店を出る。
けれど少し遅れて店から出てきた彼は、何も言わずに隣に並んだ。
こちらを窺ってるような気配は感じたけど、そんなもん無視よ無視。 おごられた程度で機嫌なおるほど安くないんだから。
そうして、しばらく無言で歩きながら、私は計画を練る。
とりあえずこのまま負けっぱなしになるのなんて、絶対ごめんだし。
やっぱ今の世の中、恋人同士と言えども男女対等じゃないとね。
ドキバクうるさい心臓を意識の外へ追いやって、私はゆっくり手を伸ばす。
「………!」
触れた瞬間驚いたように震えたそれは、少しだけためらった後ぎこちなく握り返してきた。
慣れてないんだ、と雄弁に語るその手に、口元が緩む。
私のよりもずっと大きくて、ゴツゴツしてて。
ずっと触れてみたかった手。
仕方ないから今日はこれで満足してあげようかな、なんて思いつつこっそり見上げた先には、いつになく嬉しそうな彼の顔。
当然よね、なんたって『ベタ惚れ』なんだから、とかって必死で考えてみたりしたんだけど。
顔が真っ赤なままじゃ、誰がどう見ても、私の負け確定だっつーの。
ああ、もう、そんな嬉しそうにするんじゃないわよ!
嬉しいのは私の方なんだから、だから私の勝ちなんだからね!
◇終◇
読んでくださってありがとうございました
お時間ありましたら
[感想送信フォーム(別窓)]から感想のお声を聞かせてください。
今後の創作の励みにさせていただきます。